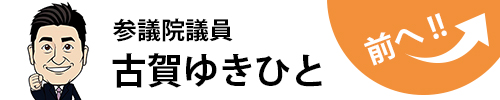コガちゃんねる~あなたの会社、よみがえれ~
2025年6月5日(木)経済産業委員会(法案質疑)
「円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案(早期事業再生法案)」
***************
【質問項目】
(1)衆議院における法案修正について
問1:【対修正案提出者】
衆議院において法案修正が2箇所行われている。まず第一条関係「目的規定の修正」の具体的な内容をご説明いただきたい。また、修正案提出に至った背景や理由、更には、この修正で期待される効果についても伺いたい。
問2:【対修正案提出者】
続いて、第14条第3項第6号関係「早期事業再生計画の記載事項の修正」について同様に、修正の内容、提出の背景や理由、また修正によって期待される効果についてご説明いただきたい。
問3:【対経済産業大臣】
日本労働組合総連合会(連合)では、早期事業再生法案の閣議決定を受けて、3月7日に談話を公表。その中で「本制度は、あくまでも金融債務に限定しているものの、これまでの他の手続による事業再生で、人員整理や労働条件の引き下げなどが頻発している実態があることからすれば、労働者保護の観点で、懸念がある」と表明されている。法案成立となれば経済産業大臣がこれを所管するわけで、大臣は、事業再生の局面における「労働者保護」の大切さ(←事業者にとっても)、また修正内容の意義についてどのように理解しているか。
問4:【経済産業大臣】
例えば「早期事業再生計画」に、労働者の雇用などに関する変更が生じる内容が記載される場合、労働組合との協議が確実に実施されるよう何らかの手続関与についてルールの整備があって然るべきと考えるが、大臣の認識はどうか。
問5:【対修正案提出者】
最後に、感想めいたお尋ねで恐縮だが、山岡議員は今国会の経済産業委員会で審議された閣法4本に対して修正案を2度提出。いずれも衆議院で成立した。こうした立法活動を振り返り、どのような感想をお持ちか。
(2)「早期事業再生法案」提出の背景/経緯について 一般的に、企業の業績や資金繰りが悪化して自力回復が難しくなると、企業は事業再生を図るために、債務の減額や免除、返済猶予など債務整理を行う必要に迫られる。我が国には方法として法的整理と私的整理の2つがあり、法的整理は、裁判所が関与して、債権者の多数決で(全会一致ではなく)事業再生に進めるが、手続開始の際に「公告」=広く世の中に知らせることが行われて、債務整理の公平性・透明性は高いが時間もかかり、その結果「事実上の倒産」「連鎖の懸念」などと社会的騒動となり、企業の取引関係に多大なマイナスの影響を及ぼす問題が指摘されてきた。一方、私的整理では「公告」はなしで、主に、金融機関などの金融債権に限定して手続を非公開・スピーディに進めることが可能。しかしそれには債権者「全員」の同意が必要とされている。
問6:【対経済産業省】
債務者たる企業がその事業価値を維持しながら(例えば外資系金融機関など)一部の金融債権者の反対を抑え、事業再生を図るには、以前から、現行の法的整理・私的整理の「二分法」では「十分に機能しない恐れがある」。従って「私的整理に多数決原理を導入すべき」との議論が、倒産/再建の第一人者、また産業再生機構の委員長としてカネボウやダイエーの再建にもあたられた、弁護士で元裁判官の故・高木新二郎先生などを中心に(2014年頃には)本格化していたと聞く。また欧州各国では「私的整理への多数決原理」は導入済み。我が国で、法案化がかくも年月を要したのにはいかなる事情があったのか。
問7:【対法務省】
我が国には「倒産法」という名前の法律はない。あるのは、経済的な破綻状況に至った企業または個人について、その財産の清算もしくは再建、また債権者への配当を定める法律の総称としての、いわゆる「倒産法」であり、破産法、民事再生法、会社更生法などが含まれると理解している。そもそも倒産という言葉は、主に、企業が経済的に破綻した場合に使われる事実状態を表す用語であり、法律用語ではないと聞く。とはいえ会社更生法の申立てが行われ、会社が更生される方向の場合でも、社会的には「倒産」と表現される。実際には「再建型手続」と「清算型手続」のどちらで進むかによって、会社の行く末は大きく異なるわけで、企業が再建を目指しているのに、「倒産」のレッテルで企業価値の棄損を背負うのは、社会としても決して有益でなく(これが今回の法案の必要とされる理由の1つでもあるわけであり)、いわゆる「倒産法」の法体系の中で、「再建なのか清算なのか」の道筋に沿って、何らかの名称変更や区分の再整理を行うなど、検討の余地があるのではないか。
(3)創設される制度のスキームについて 次に、今回の法案で創設される制度の具体的なスキームについてお尋ねする。
問8:【対経済産業省】
私的整理の中には、すでに「事業再生ADR」制度(=ADRとは英語で、Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続の意味)、「訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る」という制度(事業再生ADR)が既に存在している。これに対して、今回創設される制度はどのようなスキームか。 「事業再生ADR」と比較しながら、わかりやすく説明していただきたい。
問9:【対経済産業省】
事業再生ADRでは、「(債権者・債務者)双方の税負担を軽減して、債務者に対するつなぎ融資の円滑化等を図る」こと(例えば、産業競争力強化法に基づき、手続終了後、計画実施段階における金融支援が受けられることなど)が、盛り込まれているが、新設される制度には、そのような支援措置はあるのか。(ないならば、事業再生ADRには支援措置があって、今回の新制度にはない理由(なくてよいと考える理由)を教えてほしい)。
(4)対象事業者・対象債権について
問10:【対経済産業省】
今回の制度における対象事業者は、条文上(第3条第1項などで)「経済的に窮境(きゅうきょう)に陥るおそれのある事業者」とされているが、具体的にどのような状態を指すのか。何か定義や要件があるか。(←事業再生ADRでは、経済産業省告示で「過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再生が困難であること」との規定があり、”経済的に窮境に陥った”段階を対象とすると考えられる。そうであるならば「経済的な窮境」については、窮境に陥る「おそれのない」段階、「おそれのある」段階、そして「窮境に陥った」段階と、全部で3つの段階あると考えられるが、それぞれの段階をどう切り分けているか。具体的な定義や判定基準などあれば伺いたい)。
問11:【対経済産業省】
この制度では、権利変更の対象となる債権は「金融機関等が有する金融債権に限定」されるが、そうした理由は何か。また、担保付債権について、「権利の減免」に該当する権利変更を対象外とすることは理解できるが、いわゆるリスケジュール(リスケ)にあたる「期限の猶予」についても対象外とするのは妥当なのか、と疑問を呈する意見もあるが(経済同友会)どのように考えるか。
(5)対象債権者集会における決議について
問12:【対経済産業省】
対象債権者集会での決議の可決要件は、議決権の総額の4分の3以上の同意。(単一の債権者が議決権の総額4分の3以上を保有する場合、議決権者の過半数の同意を頭数要件として加重あり)。この「総額の4分の3以上」の要件はどこから出てきたのか(3分の2、5分の4、過半数でない理由は何か)。また情勢の変化では「4分の3」要件は強化or緩和されることもあるのか。
問13:【対経済産業省】
事業再生ADRでは、債権放棄を伴う事業再生計画については、株主の権利の消滅や、役員の退任などが要件とされているが、今回の新制度ではそのような株主責任や経営者責任のあり方についてどうなっているか(またその理由)。
問14:【対経済産業省】
この制度において決議の対象は、第11条で示される「権利変更議案」だけ。一方、事業再生ADRでは「権利変更」の議案に加え「事業再生」の計画案も決議される。しかも事業再生ADRでは、資産および負債等の見込みに関する事項について、3年以内の債務超過解消および経常黒字化の要件が課される。この決議対象の違いは、どこから生じるのか。また、新制度では、事業再生の計画=早期事業再生計画の履行について決まりはあるか(なくてよいのか)。
(6)第三者機関(指定確認調査機関・確認調査員)について 今回の法案では、制度利用の要件確認をはじめ、制度の手続を監督する第三者機関(指定確認調査機関)を経済産業大臣が指定することとなっており、法案第46条第1項第5号で「対象債権者集会関連業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること」と規定されている。また、第52条で「指定確認調査機関は、第3条第1項の確認の申請を受けたときは、人格が高潔で識見の高い者であって、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者として経済産業省令で定める要件を備える者のうちから、事案ごとに、確認調査員を選任しなければならない」と、実際に担当する「確認調査員」を規定している。
問15:【対経済産業大臣】
新たな制度では、事業再生ADR制度の全会一致要件が緩和されていることを考えると、公正性や中立性をより厳密に確保したうえで、対象債権者集会関連業務を継続的に行う必要があるわけで、事業再生ADR制度よりも厳格な認定基準が求められると考えてよいか。
問16:【対経済産業省】
この制度を利用する場合、第三者機関(=指定確認調査機関)に支払う金額、確認調査員の報酬はどのようになるのか。法案第50条(業務規程)では、「料金を徴収する場合にあたっては、当該料金に関する事項」として「料金の額又は算定方法及び支払い方法」を業務規程に定めることとしてあるが、第50条第3項第2号では「料金の額等が著しく不当なものでないこと」としか、規定されていない。具体的にはどのような内容/イメージとなるのか。
(7)まとめ
問17:【対経済産業大臣】
企業再建ではとかく債務カットの行方に注目が集まりがちだが、これまでも、そして企業を再建していくプロセスで、企業を支え、企業価値を生み出すのに不可欠な「技術や人材が散逸せず」、また、従業員の協力の下で、円滑に早期事業再生計画を実施していくことが、この法案の肝(きも)と考えるが、法律を所管する大臣の認識と今後に向けての決意を伺いたい。
以上
★これからも、対談、福岡の情報発信、政治のことなど、様々なテーマでお届けしますので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします!
コガちゃんねるはこちら↓
https://www.youtube.com/channel/UCD8zC6kMUl4JWb8oqHqCReA