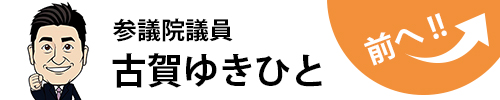コガちゃんねる~下請けいじめの連鎖を断ち切る!~
2025年5月15日(木)経済産業委員会
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」
【質問内容】
●審議会「企業取引研究会」報告書の最終ページについて
問1:【公正取引委員会】
本日審議されている下請法改正案は、昨年2024年7月から12月まで計6回にわたり開催された審議会「企業取引研究会」の議論をベースに作成された。
報告書の最終ページ「おわりに」では、ロックバンド/ザ・ブルーハーツの大ヒット曲『トレイン・トレイン』の歌詞「弱い者達が夕暮れ さらに弱い者をたたく」が引用されている(バブル最盛期の1988-89年の作品で作詞作曲は真島昌利(ましま・まさとし)氏)。
その経緯、また、そこに込められた意図・思いなど審議会を補佐した事務局よりご説明いただきたい。
*************
企業取引研究会報告書(令和6年12月)
『おわりに』
弱い者達が夕暮れ さらに弱い者をたたく
その音が響きわたれば ブルースは加速していく
見えない自由がほしくて
見えない銃を撃ちまくる
本当の声を聞かせておくれよ
今から30年ほど前にヒットした曲の一節である。
今回、現代に生きる私たちが改めてこの歌詞を聞くとき、私たちに問いかけられ続けている課題があるのではないだろうか。
本研究会が議論をしてきたテーマにおいて「弱い者達」とは、企業規模の大小を問わず、商品やサービスの価値向上を追求し、顧客に対してその価値に見合う対価を訴求するという本筋での努力を避け、自社の商品やサービスの価格を据え置く原資を確保するため、取引上の「強い立場」を利用して立場の弱い「受注者」や「労働者」の仕事の価値を評価することなく、買いたたく者のことである。
(中略) 1990年代半ばをピークに生産年齢人口が減少に転じ、国内市場が成熟期を迎えていく。こうした中で、高度経済成長を支えた商慣習は、今日においては、人目のつかない「夕暮れ」に、「弱い者達」が「さらに弱い者を」たたいて利益を確保していく要因となってしまっているのではないか。
すなわち、企業は設備や労働に投資し、新しい付加価値を高めて利益を上げるという行動ではなく、自社の商品やサービスの価格を据え置き、その原資を取引先と労働者に求めるという行動をとってきていたのではないか。
そうした中で、弱者にしわ寄せしても構わないという暗黙の了解が生まれ、それが社会的規範といえるまでに定着してしまったのではないか。
(中略) 企業の経営努力だけでは如何ともし難い、不可避的に生じる原材料等のコストの上昇があっても、転注や失注をほのめかされ、コスト負担を受注者だけが飲まざるを得ないような取引、納品された商品に瑕疵がないのに協賛金等と称して契約で定めた代金を減額するような取引、契約にない荷積みや荷下ろしを当たり前のように無償で行わせる取引、納品したのに約束手形によって 180 日間も支払を受けられないような取引等々。
本研究会で取り上げた論点は、これまで中小企業庁を始めとする関係省庁のGメンが多くの中小企業を訪問し、現場から一つ一つ拾ってきた取引先を恐れて言い出せない「本当の声」に基づいて提起されたものである。(以下、省略)
問2:【公取委員長、経産大臣、内閣府特命担当大臣】
公取委員長、経産大臣、内閣府特命担当大臣にお尋ねする。お三方は行政機関の長として本日ご出席だが、一個人として、審議会の締めくくりとなるこの文章や、引用されたザ・ブルーハーツの『トレイン・トレイン』の歌詞を読んで、率直にどのような思いが頭に浮かんだか。例えば、カラオケで歌って盛り上がったとか、自分も当時「弱い者」で悔しいことばかりだったとか、明るくても暗い話でも構わないが、個人の体験やパーソナルな語りをお願いしたい。
※行政機関の長たるお三方になぜ個人的な立場で語っていただいたかというと、実はこの報告書の「おわりに」の後段では、以下のようにも記述がある。
なお、本研究会では、主に法規制の観点から議論を行ったものであるが、デフレ型の商慣習から脱却することは法的手当てのみを行うだけでは十分とは言えない。法的手当てと併せてより一層の価格転嫁対策に係る施策を推進していくことが求められる。(中略) 法令遵守は重要であるが、「下請法さえ守っていれば良い」という意識が 仮にあるとすれば、それは事の本質を捉えていない。
前回の委員会で伊藤大臣にこうお尋ねしました。『趣旨説明によれば、改正案の中核は「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」や「規則及び支援の対象となる事業者の範囲の拡大」であろう。ならば「サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる」ことや「我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにする」ことは、改正案にとってどのような位置づけか』。
答えはシンプルでそれは「法改正の目的」とのことでした。本日の質問で分かると思うのですが、価格転嫁や価格転嫁の実現によって実現される「中小企業の物価上昇に負けない賃上げ」が、法的手当てのみで自動的に達成されるというのはなかなか難しい。私たち一人一人の意識の変革をはじめ、政府のあらゆる政策資源も含めて総動員しないと、社会に長年しみ込んだ慣行は変わらないのかもしれない。それゆえ冒頭で敢えて法律論を踏み越え、気持ちの領域に立ち入らせていただき、行政機関の長の共感力を引き出し、「弱い者」に思いをはせながら真の目的である「価格転嫁・賃上げの実現」に少しでも近づけられないかと考えた次第です。
それでは以下、法改正の具体的な内容についてお尋ねします。
***********
●法改正が必要となった背景=我が国産業構造について
問3:【中小企業庁】
改正案のベースとなった「企業取引研究会」の報告書に記載もあるが、我が国の企業規模別の、ここ20年間の「労働生産性」や「価格転嫁力」について説明をいただき、そこから大きな構図として何が読み取れるのか解説をお願いしたい。
●価格交渉/価格転嫁に関する厳しい現実について
問4:【経産大臣】 価格交渉は十分改善しない、価格転嫁も大幅アップしない中、各種統計によるとこの5年で、仕入れ価格が上昇したことや価格転嫁できなかったことに起因する「物価高倒産」について、2020年の97件から、2021年の138件、2022年の320件、2023年の775件。そして昨年2024年には933件と過去最多を大幅更新。11年ぶりに1万件を突破した倒産件数の1割近くに及んでいる模様。 (業種別:建設業26.8%、製造業20.8%、運輸・通信業16.6%、小売業16.1%)。 (今のご時世、私的整理や廃業、M&A、合併/吸収など倒産以外の選択肢も増えて、昨年の倒産1万件は過去の基準ならば1万5千件ぐらいに相当するだろうと、危機感を強める専門家もいるが)経産大臣は、現行の下請法の下で起きている「物価高倒産」の急速な増加現象についてどのような認識をお持ちか。
問5:【公正取引委員会】
今回の改正案の核心部分である「協議を適切に行わない代金額の決定」の禁止は、条文ではどのように規定されているか。一般人でも分かるよう、条文の読み方、また、どういう場合が禁止に当てはまるかの認定要件を(限定条件などあるならそれも分かりやすく)体系的に解説していただけないか。 [下請法改正案:第5条第2項第4号] 中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること。
問6:【公正取引委員会】
改正案の成立によって「協議を適切に行わない代金額の決定」が禁止されると、法の目的である「サプライチェーン全体で適切な価格転嫁」は実現するか。 「我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できる」ようになるか。 仮に100%自動的に価格転嫁の実現・賃上げ原資の確保となるわけでないならば、それはどのような場合、どのような状況/理屈でそうならないことがあり得るか。(※法の成立で法の目的が100%実現するとはならない事情を説明されたし)
問7:【公正取引委員会】
韓国では一昨年の2023年、中小企業や下請業者等との取引価格に原材料価格の変動を反映させる内容に下請法が改正された。この「下請代金連動制度」は取引価格の10%以上を占める原材料価格が一定割合以上変動した時これに連動して取引価格を調整する制度と聞くが、政府は把握しているか。今回の法改正でこのような制度の導入は議論されたか。
問8:【公正取引委員会】
今回の法改正の内容=協議を適切に行わない代金額の決定を禁止するだけでは、改正の目的=価格転嫁の実現が必ずしも保証されないならば、韓国の下請法と同様にオートマチックに下請代金が「連動」する制度の方が確実で良いはずだが、そのような制度を採用しない理由を説明してほしい。(例えば、憲法の経済的自由権などに抵触するからか)
●価格交渉・価格転嫁に関する数値目標を掲げる必要性について
問9:【経産大臣】
「企業取引研究会」報告書にも「法的手当てのみを行うだけでは十分とは言えない。法的手当てと併せてより一層の価格転嫁対策に係る施策を推進していくことが求められる」との記載もある。法の目的「価格転嫁・賃上げの実現」に近づくには、法的手当てにあたる改正案に併せて、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁や、中小企業における物価上昇に負けない賃上げ等について何らかの数値目標を要所要所で掲げる必要があるのではないか(不要ならばその理由)。 また経産省として法改正後の価格転嫁・取引適正化にどう取り組む考えか。
●改正案各論1(下請代金の支払条件)
問10:【中小企業庁】
手形払いの禁止、特に、受取人の利用意向調査における「やめたくない」層が(9.8%)=約1割は存在するが、何か対応を検討しなくてよいか。
●改正案各論2(下請法逃れ防止のための適用基準の追加)
問11:【公正取引委員会】
下請法の適用基準の追加について改正案に盛り込まれた「従業員数」基準以外に審議会では「取引依存度」や「資本金変更行為」などの基準案があったと聞く。これらはどのような内容であり、なぜ採用されなかったのか。(「下請法逃れ」を防ぐという観点では、選ばれなかった基準も加えて、「資本金」「従業員数」「取引依存度」「資本金変更行為」の4基準のどれかに該当すれば対象になるとして幅広く網をかける発想はなかったか。)
問12:【公正取引委員会】
下請法や独占禁止法では、フリーランス、個人事業主、建設業などはどのような扱いと整理されているか。また今後、新しい働き方/新たに生まれた職種の場合、対象となる/ならないはどのように考えるのか。
●改正案各論3(物流に関する商慣行の問題)
問13:【公正取引委員会】
改正案が成立すると、いわゆる「物流に関する商慣行の問題」=荷積みの強要の問題などには、具体的にどのような効果があるか。例えば、取極め/対価なしに何かをさせるのはダメだろうが、何かをさせないのはどうか。「8時集合」と言えば「7時59分まで来るな、8時1分では遅い」と厳命され渋滞前の朝早くから路肩駐車で調整せざるを得ない状況は変わるか。
●改正案各論4(「下請」という用語の見直し)
問14:【公正取引委員会】
「下請」という用語の見直しについて、どのような検討がなされているか。(表面的に言葉を変えるだけでは問題が水面下に隠れるだけとの批判もある)
●まとめ(法改正・委託/受託取引の適正化に対する決意)
問15:【公取委員長、経産大臣、内閣府特命担当大臣】
今回の法改正、また、法改正後の中小企業の取引適正化をめぐる課題に対して、各行政機関の長としての決意を伺いたい。
以上
★これからも、対談、福岡の情報発信、政治のことなど、様々なテーマでお届けしますので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします!
コガちゃんねるはこちら↓
https://www.youtube.com/channel/UCD8zC6kMUl4JWb8oqHqCReA