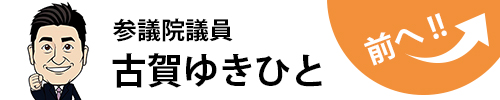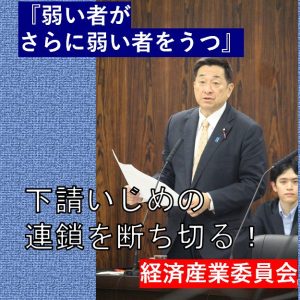コガちゃんねる~中小企業が価格転嫁して賃上げができるように!~
2025年5月13日(火)経済産業委員会(法案審議1回目)
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」
【質問内容】
●政府提出の下請法改正案に対する衆議院における施行期日に関する附則の修正の意義について 【衆議院における修正案提出者】
●トランプ関税に関する我が国の交渉状況、また他国の関連動向に対する認識ついて【経産大臣】
●トランプ政権が目指しているアラスカLNG開発に対する政府の認識、今後の取扱について【資源エネ長官、経産大臣】
●2022年1月の制度開始以来4年目で初めてゼロとなったガソリン補助金について【資源エネ長官、経産大臣】
●公正取引委員会が5/8に行ったホテル運営事業者に対する警告について【公取委員長】
●下請法改正案による「サプライチェーン全体での価格転嫁の定着」に関する実効性、数値目標設定の必要性について 【内閣府特命担当大臣、経産大臣】
*********************
●「トランプ関税」全般について【経産大臣①、内閣官房②、経産省③】
①先週5/8(木)米英両政府は貿易交渉の合意を発表。米国は英国製自動車の輸出について10万台まで税率を10%とする(←27.5%)。一方英国はボーイング社の航空機100億ドル相当を購入するなどの内容(※英国の対米輸出には最低10%の関税(←2023年は2%未満))。また米中でも閣僚級会合が開催。ベッセント財務長官から「大きな進展があった」との発言があった。 これらの情報を政府はどう把握し、どのように評価/分析するか。 特に米英合意は今後の米国との交渉にどう参考にできるか(できないか)。
②前回の日米交渉2回目は、日本側は赤澤大臣1人に対して米側はベッセント財務長官、ラトニック商務長官、グリア通商代表と3人。なぜ1対3なのか。 (米側が3人であることを事前に知っていたか。我が国が1人の理由は。 米側3人体制の役割分担、交渉過程や決定メカニズムはどうなっているか。)
③米国は4/29(火)自動車/部品の関税修正と追加関税の重複適用の調整を公表。 内容は、米国内で組み立てられた自動車について、その価値の15%を占める自動車部品に対する関税を1年間の減免。2年目は10%に相当する自動車部品の関税を免除(3年目以降なし)。具体的に言えば、2025/4/3~2026/4/30の間は米国で組み立てられた全ての自動車の製造者希望小売価格の合計額の3.75%(=15%×25%の追加関税)に相当する輸入調整相殺額を受け取れる。そして2026/5/1~2027/4/30の間は2.5%(=10%×25%の追加関税)に相当する輸入調整相殺額を受け取れる。また追加関税の重複適用の調整については「自動車及び自動車部品に関する追加関税の対象物品には、対カナダ・対メキシコの追加関税、鉄鋼アルミ追加関税は課さない」。更に「必要な手続変更は2025/5/16までに実施、3/4以降に輸入されたものについて遡及適用する」との複雑な内容。日本企業はカナダ/メキシコにサプライチェーンを展開中で、米国の通関現場では一連のトランプ関税の結果、理不尽な対応を余儀なくされていないか。 (※例えば、複雑怪奇な税制税率のため、通関処理日数が大幅増加しているとか、面倒なので多少高額でも速く通関できる申請を選択しているとか、先行き不透明なので一時的に輸出量を減らす/停止しているなど起きていないか)
●アラスカLNG開発について【エネ庁④、経産大臣⑤、内閣官房⑥】
④トランプ政権の目指すアラスカLNG開発は概略としてどのようなプランか。 我が国にはどのようなメリット/デメリットがあると認識しているか。 (第7次エネルギー基本計画で示された「複数シナリオ」の中で、今回のアラスカLNGを活かせる役割など、どこかに見出す余地はあるか。)
⑤ベッセント長官は4月初旬の米CNBCの取材において、「日本やおそらく韓国、台湾が多くの資金を提供する。そうすれば関税引き下げの代わりになるかもしれない」と発言。アラスカLNG開発への投資で自動車を守る発想はあり得るか。
⑥また昨日の報道によると、我が国は米側へ「日米造船黄金時代計画」という提案をしているとのこと(米国造船業の再興に向けて修繕能力の拡大、サプライチェーンの強化、また北極圏などで使われる砕氷船での協力など)。これは実際にはどのような内容で、米側の受け止めはこれまでどのような感じか。
●トランプ関税の国内影響と今後の展開について【経産省⑦、経産大臣⑧】
⑦トランプ関税のマイナスの影響は国内でも顕在化し始めている。トヨタ自動車は今年度の最終利益は前年比-34%、コマツは営業利益が943億円減少、三菱電機も営業利益が300億円ほど押し下げられると発表。こうした影響は大企業の裾野に広がる中小零細にとって懸念が大きい。そこで立憲民主党では先月4/18に「トランプ関税対策第1弾」として中小企業の資金繰り支援策を発表。(内容は「トランプ関税により大きな影響が出ることが想定される中小企業や製造業の資金繰りを支えるため、リーマンショック後の「金融モラトリアム法(借金返済の猶予・減免)」の復活、コロナ禍の「ゼロゼロ融資(金利なし、担保なし)」の再開の実現」や「雇用を維持する企業を支援するため、雇用調整助成金の要件をコロナ禍なみに緩和する」ことなど)。前回の経済産業委員会より3週間経過しているが、その後の政府の現状把握、対応はどう展開されているか。
⑧日米交渉はスケジュール的に今後どのような見通しか。来月はカナダでG7、7月は我が国で参議院選挙。時間は日本とアメリカどちらの味方と考えるか。
**************
●下請法改正案について【内閣府特命担当大臣⑨】
⑨趣旨説明によると改正案は「協議を適切に行わない代金額の決定の禁止」「規則及び支援の対象となる事業者の範囲の拡大」が核心部分。それでは「サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる」ことや、「我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにする」ことは改正案にとってどのような位置づけとなるか。
●法改正が必要となった背景=我が国産業構造について【中企庁⑩、公取⑪】
⑩改正案のベースとなった令和6年12月の審議会「企業取引研究会」報告書に記載があるが、我が国の企業規模別のここ20年間の「労働生産性」や「価格転嫁力」について説明/その分析を解説していただきたい。
⑪改正案の成立で「協議を適切に行わない代金額の決定」が禁止されると「サプライチェーン全体で適切な価格転嫁」は実現するか。「我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できる」ようになるか。仮に100%自動的に価格転嫁の実現・賃上げ原資の確保となるわけでないならば、それはどのような場合、どのような事情/原因でそうならないことがあり得るか。(※法の成立で法の目的が100%完全な実現とはならない事情を説明されたし)
●価格交渉/価格転嫁に関する厳しい現実について【経産大臣⑫、公取⑬】
⑫価格交渉は十分改善しない、価格転嫁も大幅アップしない中、帝国データバンクによると、この5年で、仕入れ価格が上昇したことや価格転嫁できなかったことに起因する「物価高倒産」は2020年の97件から、2021年/138件、2022年/320件、2023年/775件、そして昨年2024年は933件と過去最多を大幅に更新。倒産全体の1割を占めた(業種別では建設業26.8%、製造業20.8%、運輸・通信業16.6%、小売業16.1%、卸売業11.5%など)。現行下請法の下で起きている「物価高倒産」についてどのような認識か。
⑬韓国の下請法では2023年10月、中小企業や下請業者などとの取引価格に、原材料価格の変動を反映させる下請法等の改正が施行された。この「下請代金(納品代金)連動制度」は取引価格の10%以上を占める原材料価格が一定割合以上変動した場合、これに連動して取引価格を調整する制度と聞くが、これについて、政府はどのように把握/認識しているか。 (今回の法改正でこのような制度の導入は検討されたのか) (今回の法改正では盛り込まれていないが、その判断理由など教えてほしい)
●下請法改正に伴う数値目標設定の必要性について【経産大臣⑭】
⑭サプライチェーン全体での適切な価格転嫁や、中小企業における物価上昇に負けない賃上げなどについて、政府として何らかの数値目標を要所要所に設定する必要性があるのではないか(不要と考える場合はその理由)。
●衆議院における附則修正について【修正案提出者⑮⑯】
⑮政府提出の下請法改正案に対する衆議院における施行期日に関する 附則の修正について、どのような経緯で修正提出に至ったのか。
⑯施行期日に関する附則の修正の意義について、どのように考えるか。
以上
★これからも、対談、福岡の情報発信、政治のことなど、様々なテーマでお届けしますので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします!
コガちゃんねるはこちら↓
https://www.youtube.com/channel/UCD8zC6kMUl4JWb8oqHqCReA