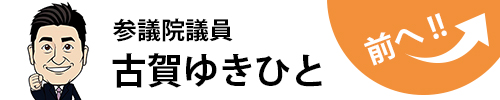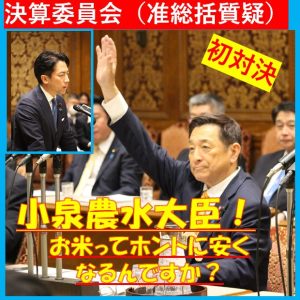コガちゃんねる~脱炭素のコストは増えるのに「経済が成長する」とは?~
2025年5月27日(火)経済産業委員会(法案質疑2回目)
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」
***************
【質問項目】
●GX推進法改正案における成長志向型カーボンプライシング構想など今後の制度設計の方針などについて
●今回の法案(GX推進法と資源法)の一括化について
●資源法改正案における環境制約の面、資源制約の面、成長機会の面での改善可能性などについて
***************
【質問内容】
(1)「成長志向型」カーボンプライシング構想について (※まずは制度全体にかかわる論点についてお尋ねする)
問1:【対GX担当大臣】
政府はどのような意味で、「成長志向型カーボンプライシング」とか「脱炭素成長型経済構造」などの言葉づかいをしているのか。そもそもカーボンプライシングも化石燃料賦課金も(税金ではないが)シンプルにコストを課すもの。ある専門家に言わせると(例えば常葉大 山本隆三名誉教授)「成長志向型CPと言っていますが、消費者と産業に負担を求めるCPが成長につながるわけがありません」とのこと。政府はカーボンプライシングの導入について「早期に取り組むほど将来の負担が軽くなる仕組みとすることで、意欲ある企業のGX投資を引き出す」としているが、原理的に考えて、脱炭素のコストは増えるが製品は変わらないのに、なぜ「成長志向」や「成長型経済構造」につながるかその理屈を説明してほしい。
問2:【対内閣官房】
「成長志向型CP」や「脱炭素成長型経済構造」のロジックには暗黙の前提があって、企業などプレーヤー全員が同じ脱炭素の制約や条件の下に入ることが要件となっているのではないか。すなわち脱炭素化を同様に義務づけられれば(そのコストは全員平等に課されるわけでそれならば)、脱炭素に優れた者・秀でたサービス・商品がマーケットで勝ち上がっていく。そうした「前提」があってこそ初めて「成長志向型CP」の概念は成立するのではないか。
問3:【対GX担当大臣】
そうだとすると法案で措置される排出量取引制度を国として持つのは当然で、例えばEUのCBAM(シーバム:炭素国境調節措置=英語でCarbon Border Adjustment Mechanismの略:EU域外から輸入される製品に、EU同様の炭素価格に相当する価格を課す制度)などが実際に開始されれば、我が国も同様の制度なしには海外市場で通用しない。ただ前述の「前提」が不十分のうちは、現実の制度運用やその強度などは、気候変動の実態や各国動向の度合いなども注視しながら適宜適切に行うという理解でよいのか(いわゆる「キャップ」の設定の議論もそこに関連すると考えてよいか)。 (※次に、制度各論で特に気になる点についてお尋ねする。)
問4:【対内閣官房】
制度設計で話の出ているベンチマーク方式(=業種ごとに、各社の製品生産量あたりの排出原単位を比較して、同業種内の上位〇%に相当する水準をベンチマークとして企業ごとの割当量を決定する方式)は行き過ぎると業界内で企業の「優勝劣敗」をつけることにならないか。つまり脱炭素化でリードする優良企業に対し、それを追いかける企業は(未達の排出削減義務を補うため脱炭素で先行する企業に)お金を支払うわけで、逆転の一手が打てなければ、企業の体力は生物学のダーウィンの理論「適者生存・弱肉強食」のごとく格差拡大の一途をたどりかねないわけで、この点を政府はどう考えているか伺いたい。 (※ベンチマーク方式はいわば「会社同士を脱炭素化で闘わせる」制度だが、一方、グランドファザリング(年率削減方式)は「過去の自分より脱炭素化を改善する」方式であり、こっちが死ぬか/向こうが死ぬか、という話ではなく受容性は比較的高いとも考えられるがどうなのか。)
問5:【対内閣官房】
実際EUでも、最初はグランドファザリング方式で開始して、後のフェーズでベンチマーク方式に切り替えた。韓国でもベンチマークは最初、排出量の多い「石油精製・セメント・航空」で適用され、他分野はグランドファザリングとして、徐々にベンチマークの適用分野を拡大していった経緯がある。我が国は方式の切替や適用対象の変更/拡大をどのようにイメージしているか。
問6:【対内閣官房】
排出量取引制度は企業活動に対して、優勝劣敗の起こり得る、新しい理屈の、大きなコスト負担を課す制度の導入であり、法案作成のベースとなった審議会「産業構造審議会」においては、憲法との整合性も議論されたと聞く。特に、憲法第22条の「営業の自由」、第14条の「平等原則」、第29条の「財産権」の観点から、どのような議論・整理がなされたかを伺いたい。
問7:【対内閣官房】
いわゆる「カーボン・クレジット」の扱いについて、法案説明では「2026年度から開始する排出量取引制度では(中略)政府が運営するJ-クレジット・JCМの活用を認める」、そして「活用可能量の上限についても諸外国における議論の動向も踏まえつつ、次年度以降に検討する」とされ、一部は認めつつも量的上限を今後検討するとしているが、いかなる観点で、どう検討するのか。例えば、EUでは「安価なクレジットの流入で排出枠が余り、価格が下がり、域内での削減インセンティブがなくなる」ため、外部クレジットの使用不可となったと聞く。可能な限り外部クレジットの活用を認める考えと、排出者自らの削減努力を促す観点から無制限のクレジット活用を認めない考え方があるが、政府はどのように整理・検討する/しているのか。
問8:【対内閣官房】
この「カーボン・クレジット」問題に類似する論点として「石炭火力とCCS(=CO2貯留)の組合せ」を認めるかの議論がある。これを認めると、石炭使用の拡大につながるとして禁じる国もあるが(トータルとして排出量を削減できるのであるならそれでよいとの議論もあり得るわけで)、我が国はこの点について、いかなる理由でどのように整理を行っているか確認したい。
(2)今回の法案(GX推進法と資源法)の一括化について
問9:【対内閣法制局】
今回の法案は、GX推進法と資源法が一括法案/束ね法案で提出されたが、内閣法制局ではどのような場合に一括化できるとの基準をもっているか。
(※①政策の統一性基準、②条項の相互関連性基準、③委員会所管事項基準とはどのような意味か。どのように判断されるのか。3基準の全てが満たされる必要があるか(=③は①②と位置付けが異なるか)。)
問10:【対内閣官房】
今回のGX推進法と資源法とは「持続可能な発展」という幅広いロジックでは関連するが、厳密には前者/GX推進法は地球温暖化/気候変動対策の一つで、後者/資源法は廃棄物対策・リサイクル対策の中に位置付けられている。実際、廃棄物対策・リサイクル制度の法体系の中には数多くの法律が複雑に存在しており、まずは資源法と他の法律との関係を整理してご説明いただきたい。 (※例えば、プラスチック資源循環法や容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、自動車リサイクル法、また循環型社会形成推進基本法や、廃棄物処理法などと、今回の資源法はどのような関係にあるのか。つまりは、廃棄物対策・リサイクル政策全体の法体系の中で資源法がどのような役割を担っているかをご説明いただけないか。) (今の解説を聞いてGX法と資源法の一括化について一般的に考えてどうか)
問11:【対内閣官房】
「審議は国会のご判断で」とはいえ、一括化は議院内閣制の下、野党の求める充実審議の観点で大きな制約になるのは明らかで、行政を担う内閣が立法府の上流で法案を束ね、審議のあり方に影響を及ぼすのはどうなのか。また一括法案/束ね法案といっても、可決成立すれば、1つの法律でなく、別々の法律になることを考えると、審議段階においてのみ法案を一括化する/束ねることに、そもそもいかなる意義があると考えるか伺いたい。
(3)資源有効利用促進法(資源法)について ※政府は「成長志向型の資源自律経済の確立に向けた問題意識」として「環境制約・リスク」「資源制約・リスク」「成長機会」の3つを挙げており、この3点に沿って具体的な内容について質問する。
問12:【対環境省】
「環境制約・リスク」について、政府は「カーボンニュートラル実現には原材料産業によるCO2排出の削減が不可欠」として、資源循環による削減貢献の余地がある部門は全体の約36%に及ぶというが、現在のNDCの目標達成にどの程度の貢献が可能と考えるか(具体的な数値目標など検討しているか)。
【参考】:再生材の利用拡大で製品製造に係るCO2の大幅な削減効果が期待 ・アルミ缶のリサイクルでCO297%削減可能 ・スチール缶のリサイクルでCO296%削減可能 ・食品トレーのリサイクルでCO283%削減可能 ・鉄材のリサイクルでCO279%削減可能 ・亜鉛のリサイクルでCO269%削減可能
問13:【対内閣官房】
「資源制約・リスク」について、政府は、「多くのマテリアルが将来は枯渇」、また「供給が一部の国に集中」「資源国の政策による供給途絶リスク」と指摘するが、特にどの資源のリスクが高く、資源循環により依存度低減はどの程度可能と考えているか(具体的な数値目標など検討しているか)。
問14:【対内閣官房】
「成長機会」について、EUでは今後「リサイクル材含有義務」の導入が進むと聞く。例えば自動車やバッテリー、容器包装などは一定割合のリサイクル材/再生材を使用しないと輸出できなくなるおそれもでてくるが、法案の成立で我が国産業界はどの程度EUのこうした参入障壁に対応できるようになるか(具体的なロードマップなど検討しているか)。
問15:【対GX担当大臣】
気候変動への対応や循環経済の実現まで道のりは長く険しい。前回の質疑でも分かったが、今のパリ協定も国際合意として十分なレベルとは到底言えない。GX担当大臣として、この法案に限らず、どの辺りが今後、我が国にとって、また国際社会にとっても、真の意味での勝負所になると考えるか。またそこに向かって政策をどう積み重ね、かじ取りを進めていくか決意を伺いたい。
以上
★これからも、対談、福岡の情報発信、政治のことなど、様々なテーマでお届けしますので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします!
コガちゃんねるはこちら↓
https://www.youtube.com/channel/UCD8zC6kMUl4JWb8oqHqCReA