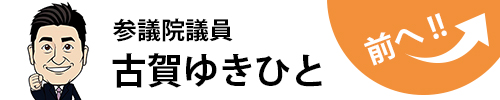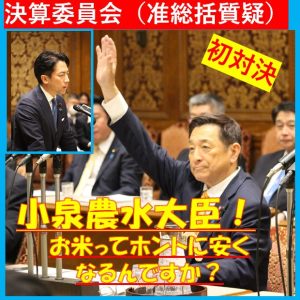コガちゃんねる~2050年カーボン・ニュートラルって日本以外の国はどう守るんでしょうか?~
2025年5月22日(木)経済産業委員会(法案質疑1回目)
「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」
【質問内容】
(1)パリ協定に基づいて各国が5年ごとに作成・提出を義務付けられている温室効果ガスの排出削減目標であるNDC(=「国が決定する貢献」、英語でNationally Determined Contribution、略してNDC)について (まずは法案の中核である「排出量取引制度」の今後の制度設計の前提となる我が国NDCの位置付けについてお尋したい。排出量取引制度は必要だが、その前提にちょっとしたズレや何らかのブレが生じただけで、実際の制度の詳細設計や運用の効果は大きく影響されるため、新しい制度を論じる前に、その前提の揺らぎというか、変動幅というか、それがどの程度かを、国益に直結する議論をする以上、明確にしておく必要があると考え、お尋ねする。)
問1:【対環境省政務2役】
我が国NDCは現在どのような内容か。パリ協定の目標「今世紀末までに気温上昇を産業革命前と比べ2℃以下、できれば1.5℃以下に抑える」に沿ったものか。また、どのような意味で「1.5℃目標に『整合的』で『野心的』な目標」と政府は言っているのかをご説明いただきたい。 (世界気象機関および国連環境計画が設立した政府間組織「気候変動に関する政府間パネル」=IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)の第6次評価報告書(2021-23年公表)では2030年までを「critical decade」=勝負の10年と位置付け、また2023年開催のCOP28で決定された第1回グローバルストックテイク(=パリ協定の掲げる目標に対し世界全体でどの程度達成できたか進捗を確認する制度)では1.5℃目標を実現するため世界全体の温室効果ガス排出量を「2030年までに2019年比で43%削減、2035年に60%削減、そして2050年に排出量を実質ゼロにする」必要があるとされている。政府は自らが基準年とする2013年の排出量から目標とする2050年の排出量ゼロを直線で結んだ経路に沿っているから『整合的/野心的』と言っているようだが、IPCCの用いる2019年比で言い換えるとどうなるか。例えば、政府NDCの「2035年の60%削減(2013年比)」を「2019年比」によって換算すると60%削減でなく54%削減となるのではないか。 立憲民主党では今年2/20に「2035年の温室効果ガス削減目標については、国際社会が求める1.5℃目標に整合する目標設定が必須であり、IPCCが示す科学的知見などを踏まえ世界平均で2019年比60%の削減が求められている。政府が基準とする2013年比に置き換えれば66%に相当することから日本は2013年比66%以上の削減目標を設定するべきである」との談話を出したが、政府としてどのように考えるか。
問2:【対環境省】
そもそも気候変動対策の国際的な枠組みでは、1997年に日本の京都で開かれたCOP3で採択された「京都議定書」が画期的なスタートであったが、最大の問題点として先進国のみに削減義務が課され、米国や中国、インドが削減義務を負わない、また第1約束期間(=2008~2012年)で排出削減義務を負う国の排出量が世界全体の四分の一にとどまってしまうことなど挙げられる。結果、我が国は議定書批准国であり続けるが、議定書の延長=すなわち京都議定書の「第2約束期間」(2013年以降)には不参加(京都議定書からの離脱)を決定した経緯がある。一方現在のパリ協定では全ての国が温暖化防止に取組むが、削減目標は各国が国情に応じて自主的に設定し、報告は必要だが、目標未達の罰則はないという内容である。まさに「帯に短し、タスキに長し」。パリ協定自体は極めて貴重/重要だが、最終版・完成版と思いにくい面も感じる。 各国のNDCを見ると「削減率」の数字は大きいが、よく見ると基準年が見事にバラバラ。(排出量は一般的に、昔に遡れば遡るほど量が多く、つまり古い年を基準年に設定すれば目標の削減率を大きく見せることが可能で)例えば、我が国の基準年は2013年だが、米国やカナダ、オーストラリアや中国、インド、ブラジルは2005年、EUや英国、ドイツ、ロシアは1990年と、基準年がだいぶ古く、逆にトルコは2012年、韓国2018年、サウジアラビア2019年と日本より基準年が新しい。また中には基準年をそもそも置かずBAU=Business As Usual(=「現状維持」「従来通り」と比べて)の表現で削減率を公表する国すら存在するのが実態だが、各国目標の削減率を同一年度比で比較すると、各国の公約の削減率はどうなのか。我が国NDCは厳しいのか緩いのか。
問3:【対環境省】
また各国のNDC一覧によると「ネットゼロ長期目標」の欄は我が国を含め、ほとんどの国が2050年となっているが、中国の2060年、インドの2070年、そして米国はトランプ政権でパリ協定離脱を宣言したわけで(中にはトルコの2053年もある)、「2050年カーボン・ニュートラル」の目標について地球全体で考えた場合、排出量の大きい「排出量大国」抜きで計算上実現できているのか教えていただきたい。
問4:【対環境省政務2役】
我が国では昨年11月NDC原案を示し、賛否の対立は当然起きたわけだが、世界に目を転じれば、より激しい活動を展開したスウェーデンのグレタ・トゥーンベリさん(当時10代)とともに有名になった思想「climate justice」=環境正義には驚かされた。最近同様に衝撃だったのは国連気候変動枠組条約の元首席交渉官(現・東大公共政策大学院特任教授の有馬純氏)が「パリ協定のせいで高コストの温暖化政策を強いられているとの議論があるが、問題はパリ協定の枠組みそのものではなく、50年全球CNという実現不可能な温度目標からバックキャストした非現実的なエネルギー転換を、自国にも他国にも強いようとする環境原理主義者たちである。50年全球CNは妄想に過ぎないが、地球温暖化を防止するという方向性は間違っていない」との考えをペーパー(電力政策研究会「EPレポート」2025年4/11 第2140号)で表明していること。2050年地球全体のカーボンニュートラルの実現というのは実は「妄想」か。 それでも「climate justice/環境正義」を追求するべきか。そしてその達成の見通しはどの程度たっているのか、副大臣の率直な実感/感想を伺いたい。
問5:【対金融庁】
冒頭「排出量取引制度は必要だが、前提に何らかのズレやブレが生じれば実際の制度設計や運用効果は大きく影響されうる」と申し上げたが、この問題の難しさは、気候変動を止めるという地球規模の命題を追いかけつつも国家として産業の国際競争力や国民の生活レベルを落とさずにそれを達成できるかという連立方程式にあると考える。そうしたなか、気になるのが米国トランプ政権のパリ協定離脱である。同氏がそれを標榜したためか、再選の決まった後、昨年末より米国大手金融機関のNZBA(ネット・ゼロ・バンキング・アライアンス)からの脱退が始まった(NZBAとは国連環境計画が事務局を務める、2050年までに銀行の投融資のポートフォリオにおける温室効果ガス排出量をネットゼロにするための国際的な金融機関の連合)。2024年12/6にゴールドマン・サックス、12/20にウェルズ・ファーゴ、12/31にシティグループとバンクオブアメリカ、年明け1/2にモルガンスタンレー、1/8にJPモルガン・チェースが脱退した。そしてわが国でも連動するよう大手金融機関が3月からドミノ倒しのように、三井住友、三菱UFJ、みずほ、野村HD、農林中金が脱退し、今や残るは、三井住友トラストグループのみと聞くがどのような状況か。
問6:【対環境省政務2役】
京都議定書(=第2約束期間から)の離脱や、現在のパリ協定の不完全さ(=全ての国が温暖化防止に取組むが削減目標は各国が国情に応じて自主設定し、報告必須だが目標未達での罰則はないことなど)について触れたが、まだまだ最終版完成版とは思えない国家間の合意であり、今後目指すべき合意について政府ではどのようにネットゼロに結び付けるイメージか戦略を伺いたい。
以上
★これからも、対談、福岡の情報発信、政治のことなど、様々なテーマでお届けしますので、ぜひ、チャンネル登録をお願いします!
コガちゃんねるはこちら↓
https://www.youtube.com/channel/UCD8zC6kMUl4JWb8oqHqCReA